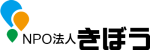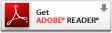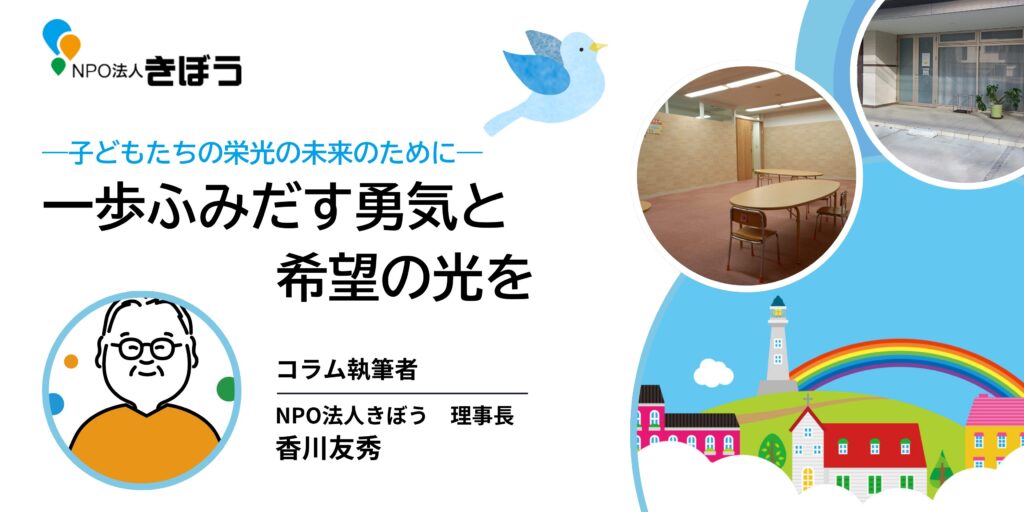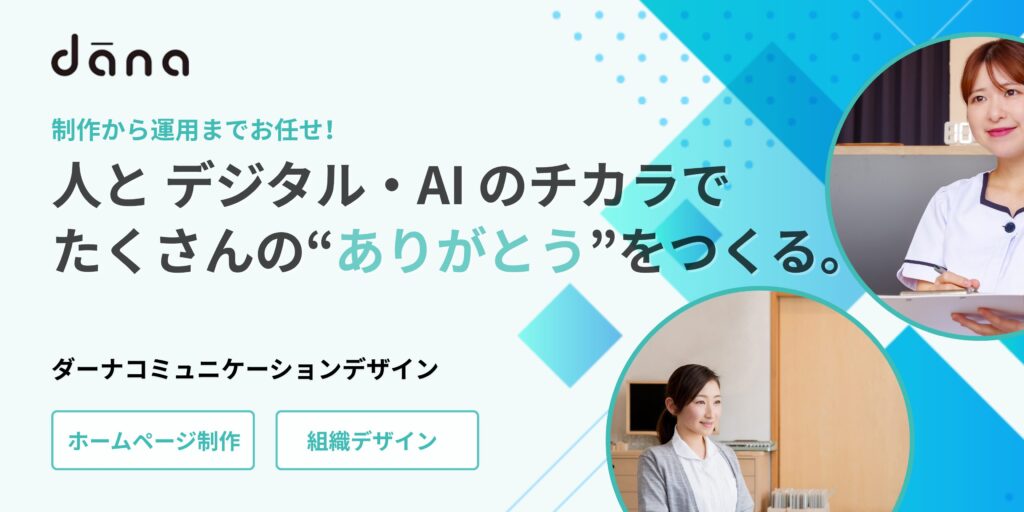発達支援プログラム






Program Contents
日常・集団生活に必要な力を身につけ
情緒の安定をはかり自己肯定感を育てます
日常・集団生活に
必要な力を身につけ
情緒の安定をはかり
自己肯定感を育てます
子ども一人ひとりの苦手なところ、得意なところを考慮しながら無理せず楽しく、様々なことに挑戦していってもらえるように取り組んでいます。
子どもたちの一人ひとりの個性・状況を考慮しながら、個別指導・集団での遊びや、日常生活でのルールを学ぶことを通して、日常・集団生活に必要な力を身につけ情緒の安定をはかり、自己肯定感を育てます。
5領域
健康・生活
運動・感覚
認知・行動
言語・コミュニケーション
人間関係・社会性
日々の支援
自然とのかかわりや季節のうつろいを感じることに重点をおいています。生活年齢や発達年齢を考慮しながら、工作、絵本、運動などの取り組みを通して、子どもの成長をお手伝いします。
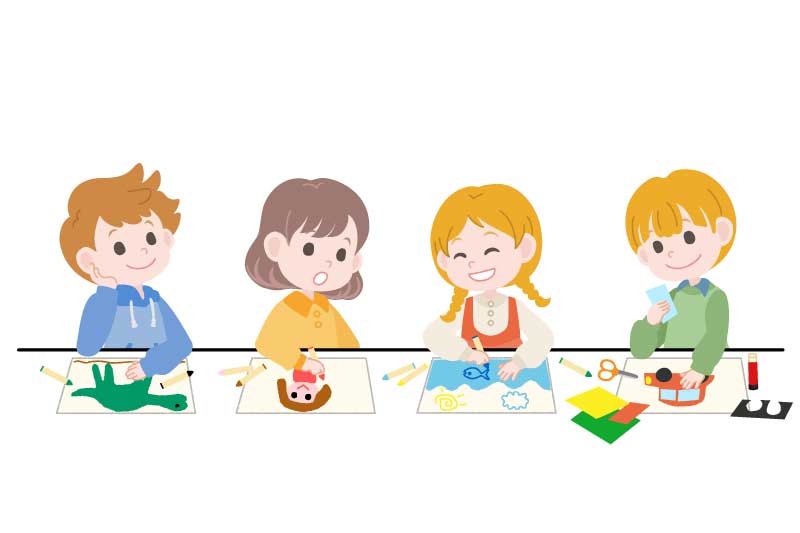
就学準備
就学前の子どもたちを対象に個別プログラムやソーシャルスキルトレーニングなどを実施します。アセスメントにより、子どもたちの状況・状態を把握し、それぞれの発達課題に応じたメニューを設定します。

リトミック教室
リトミックは、ホップ教室・ジャンプ教室とも毎週金曜日に行います。音楽を聴いて体を動かすことで、リズム、音色、曲調、強弱等の変化をより深く感じること、またそれに合わせて自己表現をすることを楽しみながら学びます。
(対応する5領域の項目)
(1)リズムやテンポの変化、先生の指示を聴き取って、動きに変化をつけたり、ポーズを決めたりすることで聴く力を養います。
→「運動・感覚」「認知・行動」
(2)ボールや棒、布などの道具を使い、五感及び触覚、固有覚に刺激を与えます。
→「運動・感覚」
(3)グループ活動を通じて、人との関りかた、思いやる気持ち、自己の確立、協調性を学びます。
→「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」
(4)音楽や音を聞いて「動く」「止まる」を繰り返すことで、自己抑制や即時反応の力を
養います。
→「認知・行動」「運動・感覚」「健康・生活」
(5)表現力・創造性・想像力・協調性・集中力・言語・数の概念・知育など、はば広い能力の発達を助長し、ボディイメージを養います。
→「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」「健康・生活」
リトミックを続けることによって、無理なく感覚に刺激を与え、豊かな感性を引き出すことや身心のバランスのとれた成長が期待できます。特に、音楽を聴くことで刺激される聴感覚は、脳の成長に大変大きな影響がある事が生理学的にも実証されています。

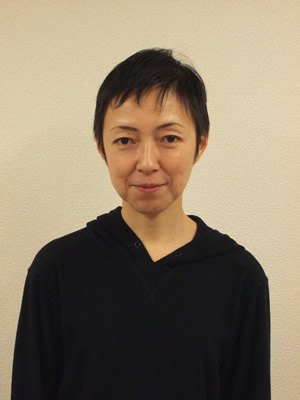
馬杉知佐(ウマスギ チサ)
リトミック教室担当

先生からのメッセージは
近日公開いたします。
読み聞かせ教室
読み聞かせは、ホップ教室は毎週火曜日、ジャンプ教室は月に1回、土曜日に行っています。読み手をしてくれるのは、フリーアナウンサーの丸子ようこさんです。
(対応する5領域の項目)
読み手が、聞き手の子どもたちに本や物語を読み聞かせるだけではなく、子どもたちが物語の登場人物になり、台詞のやり取りをしながらストーリーを進めていくこともします。また、あるテーマに沿って言葉を見つけて、その言葉をつなげてショートストーリ―を作ったりします。
読む本は、小学校の教科書、日本や世界の昔話・民話などです。子どもたちが知っている話もあれば、知らない話もあります。
「読み聞かせ」一般的に次のような効果があると言われてほか、読み手がプロのフリーアナウンサーですので、正しい発音やイントネーションが身につきます。
(1)語彙力や文法の理解が深まり、コミュニケーション能力が養われます。
→「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」
(2)ストーリーの流れや登場人物の気持ちを理解し、、文章の意味をより深く読み解くことができます。読解力が向上することで、文章問題を解く力が養われます。
→「認知・行動」
(3)物語の登場人物の感情や行動を通じて、自分ではない「他者」や「第三者」を意識することができます。これにより、人との関わり方や、共感力やコミュニケーション能力の向上、そして社会性の発達が期待できます。
→「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」
(4)物語の世界や登場人物を自分に当てはめることで、新たな自分だけのストーリーを想像し、独自のアイデアを生み出すことができます。このような創造的な思考が発達することで、問題解決能力や創造性が伸びていくことが期待できます。
「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」
(5)読み手が、プロのアナウンサーなので、正しい発音やイントネーションが身につき
ます。「言語・コミュニケーション」
(6)「椅子に座り、集中して話を聞く」ことが習慣づけられ、学校の授業に適応しやすく
なります。「健康・生活」「人間関係・社会性」
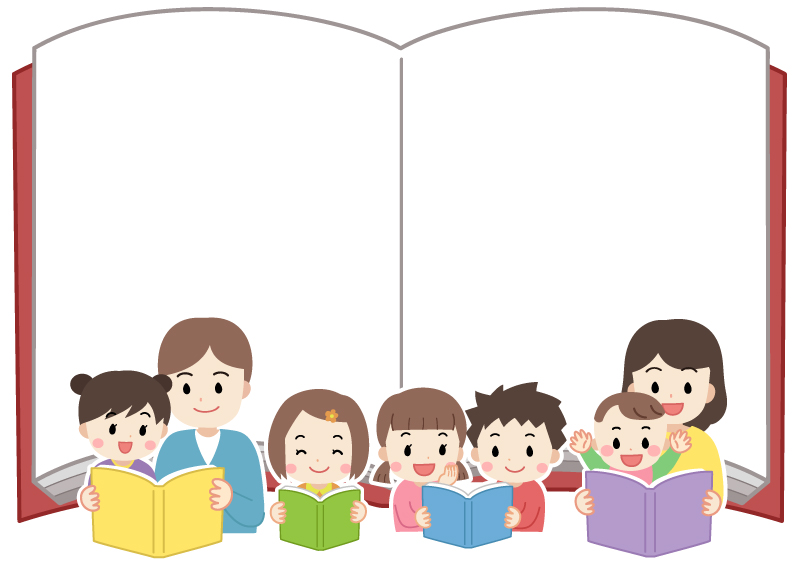

丸子ようこ(マルコ ヨウコ)
読み聞かせ教室担当

体操教室
体操は、ホップ教室が毎週水曜日と土曜日、ジャンプ教室が毎週木曜日と土曜日に行っています。マットや跳び箱、鉄棒、平均台などを使って、外遊びの要素を取り入れた運動をしています。水曜日と木曜日は、より外遊びの要素を取り入れて基本的な体の動かし方を学びます。土曜日は、器械体操の要素を取り入れ、体育で行うような種目を学びます。
(対応する5領域の項目)
(1)走る、跳ぶ、伸び上がる、回転するなどの運動を行うことで、「体力つける」「筋力
をつける」「体の柔軟さを増す」ことが期待出来ます。
→「運動・感覚」「健康・生活」
(2)身体の位置や動き、力加減を感じる感覚(固有覚)や身体の傾きやスピード、回転を感じる感覚やバランス感覚(前庭覚)、そして力をコントロールしたり、自分の位置を確認したりするための「手のひら」や「足の裏」などの感覚(触覚)が養われす。
→「運動・感覚」
(3)目と手足を含めた体を連動させる感覚や、自分の感覚と体の状態を一致させる感覚
が養われます。
→「運動・感覚」「認知・行動」
(4)これらの感覚や動きが元になり、ボディイメージが身についてきます。
→「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」
(5)挨拶する、指示を聞く、順番を守る、姿勢を保つ、周囲の状況に応じて動く、協力
して準備や片付けをするなど、集団行動に必要なスキルも身につきます。
→「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」
私たちは、ふだんの生活で「固有覚」、「前庭覚」などの感覚刺激をそれほど意識することなく受け取っていますが、それを過度に感じてしまう人や、適切に受け取れない人がいます。子どもであれば、授業中などにボーっとしたり、動きまわったりして、先生から何度も注意されてしまい、ついには、学校生活につまずきを感じてしまうことあるかもしれません。
ボディイメージとは脳の中にある自分の身体に対するイメージのことです。自分自身の身体の輪郭(形)や大きさ、位置などを把握する力を「身体の地図」と言い、どのように身体をうごかすのか、自分にはどの程度の運動能力があるのかを把握する力を「身体の機能」と言います。ボディイメージは触覚・固有受容覚・前庭感覚を元に形成され、普段はほとんど意識されることはありませんが、「歩く」「走る」「跳ぶ」「立つ」「座る」「食べる」「飲む」など日常の様々な場面で働いています。
※参考 スポーツ庁Web広報マガジン“デボルターレ”より「運動ができるようになると、アタマもよくなる!? 専門家に聞く!子供の能力を引き出すためのメソッド」 (https://sports.go.jp/tag/kids/post-20.html)
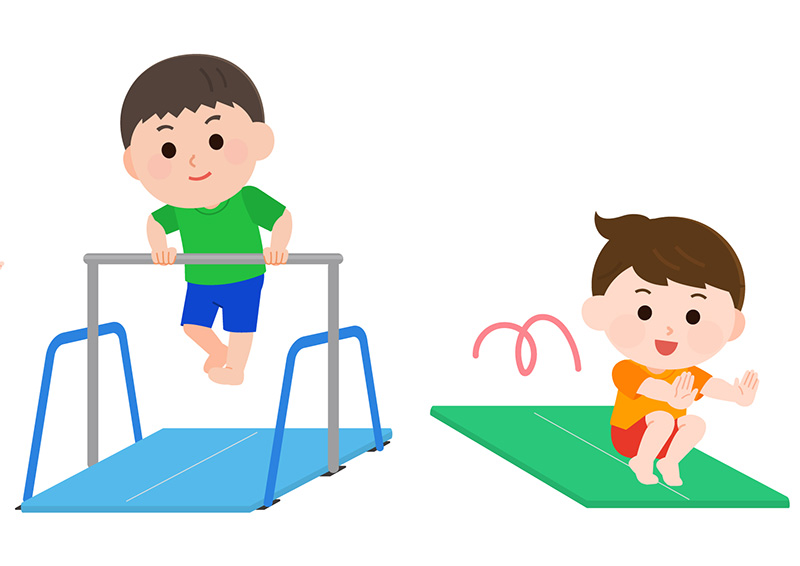

森本 章路(モリモト ショウジ)
体操教室担当


森本圭子(モリモト ケイコ)
体操教室担当

先生からのメッセージは
近日公開いたします。
運動の発達支援
生涯にわたる健康な身体の基礎は、幼少期に形成されます。3歳から5、6歳までの幼児期は、運動機能発達期といわれ、基本的な運動能力が形成される時期です。
「落ち着きがない」「少し変わった行動をする」子どもの中には、体力的には秀でているのに、日常の基本動作ができないことで、自己肯定感が育めない例が少なからずあります。これは、幼児期に運動能力が十分に獲得できす、体を上手に操ること(体育的巧緻性)ができないため、と推察されます。
この体育的巧緻性は、幼児期の外遊びで育まれるものとされていますが、現代生活の環境下では、外遊びが十分にそして継続的にできない状況にあります。
運動療育では、体育的巧緻性の基礎となる平衡感覚、固有覚、触覚の基礎感覚の獲得を目指します。具体的には、外遊びの代替え運動となる、でんぐり返りや壁逆立ちなど、家庭でもできる運動を教えていきます。
体操の指導経験が豊富で、自らも体操教室を主催されている先生が指導します。


森本 章路(モリモト ショウジ)
体操教室担当

先生からのメッセージは
こちらをクリック!

森本圭子(モリモト ケイコ)
体操教室担当

先生からのメッセージは
こちらをクリック!
学習支援
学習支援は、ホップ教室が月曜日、ジャンプ教室が月曜日〜水曜日に行っています。
ホップ教室では、年長クラスと年中以下のクラスに分かれて行います。
年長クラスは、みんなでカルタやビンゴゲームをしたあと、就学を念頭に置いたプリント学習をします。プリントは、運筆・名前の練習・数字の練習・めいろ・点つなぎ・積木問題などのほか、個々の特性や得意不得意に応じて、「目と手の連動」「集中力の維持」「視機能トレーニング」を目的とした課題をします。
また、年中以下のクラスは、ごっこ遊びやフラッシュカード、トランポリン、マグネットブロックなど、遊びながら想像力・表現力・体幹・視機能を高めるアプローチをします。
ジャンプ教室では、それぞれの学年や習熟度、及び特性に応じた課題をします。時間は1時間程度です。
プリント学習が主で、比較的やさしい課題、少し考える課題、チャレンジングな課題が混ざっています。また、「学び直し」も念頭に入れているので、同じ課題をある程度続けることが多いです。そして、ある課題について十分に定着したと判断すれば、その課題の難度をあげていきます。
子どもたちの学びの形は、一人一人違います。また、直線的に伸びていくものでもありません。凹凸を繰り返しながら、その子に応じた傾きでの右肩上がりの線になります。
ジャンプ教室では、一人一人の定着度や習熟度を見ながら、その子に合わせたスピードで学習支援を行います。
また、プリント学習以外に、道具を使った視機能トレーニング、手先指先を使う課題、身体や姿勢を整える運動なども行います。
課題が終わった後、退所時刻までは自由遊びの時間になります。何をするかは、子どもたちが話し合いで決めます。全員が同じことをしたいわけではないので、身体をうごかしたい子はドッジボールなど、そうではない子は、ボードゲームなどをして過ごします。
→「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」

話し合い活動
ジャンプ教室では、話しあい活動に力を入れています。学習支援の項目で述べた学習課題終了後の話し合いのほか、原則第1土曜日に、その月の土曜日の午前中をどう過ごすかを決める話し合いをします。進行係は、原則として小学校高学年以上の子です。
話合いにはルールがあります。「話し合いの場を妨害しない」、「人が話しているときは最後まで聞く」、「テーマと違う話はしない」、「人の意見をけなさない、笑わない」、「話し合いで決まったことには従う」など、当たりまえのことですが、話し合いの前に指導員が徹底します。また、話し合いの最中に、ルール違反があったときや違反しそうなときは声掛けをして注意を促します。
決めることは、話し合うテーマによって、一つだったり複数だったりします。複数の場合は、少数意見も生かされるよう指導員が配慮します。
話し合い活動を続けていると、「面白い」「楽しそう」「やってみたい」とメンバーが感じるけれども、「実際に行うのは難しい」という意見が出てきます。そうしたときは、「じゃぁ、どうすればできるか」について意見を出し合って、実現可能性を探っていきます。
そして、そのままではないけれども、オリジナルの意見を出した子も、「こうすればできそう」と意見を出してくれた子も含めたメンバー全員が納得する形で結論がでたときは、とてもうれしいです。
この活動を通して、子どもたちは「自分が伝えたいことを、出来るだけ正確に伝える」「人の意見を最後まで聞き、それを尊重する」「自分と違う考えを持っている人がいる」「みんなで決めたことに従う」「少数意見について、どうのように配慮するか」など、子どもたちのこれからにとって大切なことを学びます。
そして何よりも「折り合いをつける」ことを学びます。
→「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」

造形活動
ホップ教室では、毎週木曜日に造形活動をしています。よく伸びて、扱いやすいお米の粘土を使った「粘土遊び」と、月に一度「季節の工作」をします。お米の粘土は「米粉」「塩分」「水」でできていて、アレルギーの心配が少なく、安心して遊ぶことができます。
「粘土遊び」は、指や手を使って、粘土を丸める・のばす・整える・混ぜる・くっつけるなどの作業をしながら、型で抜いたり、好きな形を作ったりします。
「季節の工作」は、節分や母の日、ハロウィンなど季節の行事にちなんだものを作ります。細かい部品は指導員が作りますが、子どもたちは、大きな部品をはさみで切ったり、大小の部品を糊付けしたりして完成させていきます。
手や指には、脳につながっている神経がたくさんあり、動かすことで脳が刺激されます。この脳への刺激は、目と手を連動させる協応運動の土台となります。
作品はブログで紹介していますので、ブログのページもぜひご覧ください。
→「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」

ホップ教室、ジャンプ教室の決まり事
ホップ教室とジャンプ教室では、来所後と退所前に必ず行う「決まり事」があります。また、ホップ教室では、プログラム開始前に「始まりの会」、終了後に「終わりの会」を行っており、ここでも「決まり事」があります。
これらの決まり事を実践することで、子どもたちはいろんなことを学び、身に付けて行きます。
くわしくは、「ホップ教室の支援内容と5領域の関係」(PDFファイル)「ジャンプ教室の支援内容と5領域の関係」(PDFファイル)をご覧ください。
→「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」
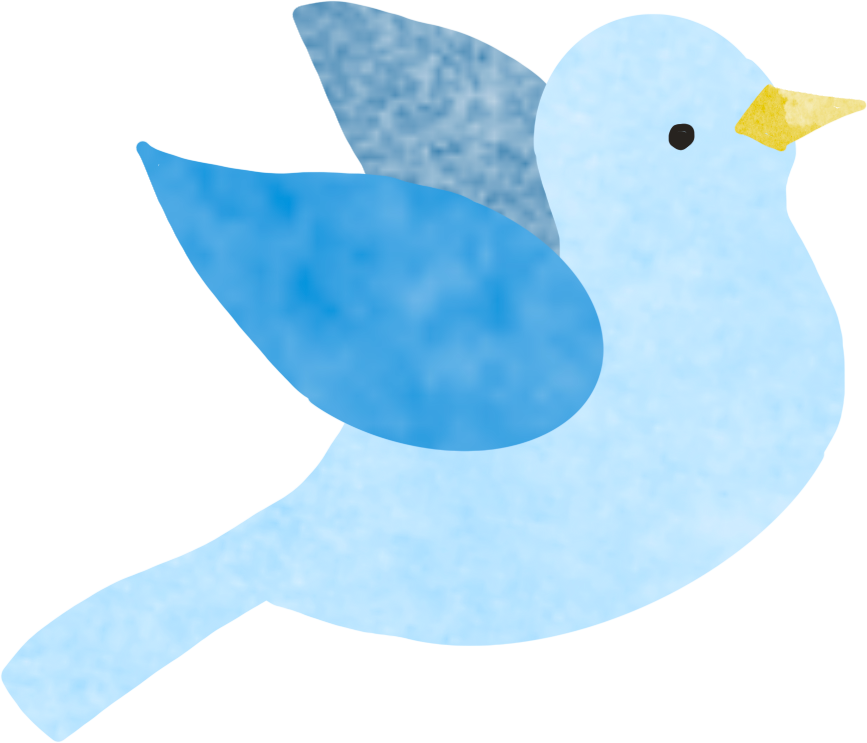

対象:未就学児
児童発達支援
曜日別発達支援プログラム
新しい発見と体験。
楽しみをいっぱいふくらませよう
営業日:月曜日~土曜日
(「国民の祝日に関する法律」で定められた休日、事業所が定める夏季休暇及び年末年始休暇を除きます)
月~金曜日 9:30~18:30
土曜日 9:00~18:00
(サービス提供時間とは異なりますので、ご注意下さい)
-
ご不明な点はご相談ください。
1
-
プログラムを実施する時間帯を設けています。詳細は、お問い合わせください。
2
-
長期休暇(夏休み等)についてはご相談ください。
3
-
当事業所では送迎を行っておりません。 保護者様ご自身で送り迎えをしていただくか、 他の移動支援を利用いただくようお願い申し上げます。
4
※下記の表は横方向にスクロールして閲覧できます。必要に応じて画面をスワイプしてご覧ください。
| サービス提供時間 (下段:学校休業日) | 発達支援の内容 (※は時間指定あり) |
|
|---|---|---|
| 月曜日 | 10:00~16:30 | 知育・就学準備等 (14:30~16:30) |
| 火曜日 | 10:00~16:30 | ※絵本読み聞かせ (14:30~16:30) |
| 水曜日 | 10:00~16:30 | ※運動教室 (14:30~16:00) |
| 木曜日 | 10:00~16:30 | ※季節の工作(月1回) (14:30~16:30) |
| 金曜日 | 10:00~17:00 | ※リトミック (14:30~16:30) |
| 土曜日 | 9:30〜16:00 | 動画鑑賞・体操 (10:00~14:30) |

対象:小学生・中学生・高校生
放課後等デイサービス
曜日別発達支援プログラム
新しい発見と体験。
楽しみをいっぱいふくらませよう
営業日:月曜日~土曜日
(「国民の祝日に関する法律」で定められた休日、事業所が定める夏季休暇及び年末年始休暇を除きます)
月~金曜日 9:30~19:30
土曜日 9:00~18:00
(サービス提供時間とは異なりますので、ご注意下さい)
-
ご不明な点はご相談ください。
1
-
プログラムを実施する時間帯を設けています。詳細は、お問い合わせください。
2
-
長期休暇(夏休み等)についてはご相談ください。
3
-
当事業所では送迎を行っておりません。 保護者様ご自身で送り迎えをしていただくか、 他の移動支援を利用いただくようお願い申し上げます。
4
※下記の表は横方向にスクロールして閲覧できます。必要に応じて画面をスワイプしてご覧ください。
| サービス提供時間 (下段:学校休業日) | 発達支援の内容 (※は時間指定あり) |
|
|---|---|---|
| 月曜日 | 15:00~18:30 (10:30~17:30) | 学習支援 |
| 火曜日 | 15:00~18:30 (10:30~17:30) | 学習支援 |
| 水曜日 | 15:00~18:30 (10:30~17:30) | 学習支援 |
| 木曜日 | 14:30~18:00 (10:30~18:00) | ※体操(低学年対象) (15:00~16:30) |
| 金曜日 | 15:00~19:00 (11:00~19:00) | ※リトミック (17:00~18:30) |
| 土曜日 | 9:30〜16:30 | ※小集団でのSST (9:30~14:00) ※体操(高学年対象) (15:00~16:30) |